このページでは、暮らしのレシピになる様々な情報を掲載。読者や編集部員の質問「昆布の出汁を取るのはなぜ水?お湯を沸かしながらじゃダメなんですか?」に、ズバッと結論から回答しています。

昆布を漬けて出汁を取るのはなぜ水なのですか?お湯を沸かしながらじゃダメなんですか?
昆布の出汁というと、日本の料理に欠かせない基本の一つ。この昆布の出汁を取る際、なぜ冷たい水を使用するのか、そしてなぜお湯を沸かしながらではダメなのか、この疑問を持ったことはありませんか?
お湯を沸かしながら出汁をとったほうが効率的に思いますが、乾燥昆布のパッケージの裏などは決まって「昆布を水に2時間漬ける」など書いてますよね。また、「沸騰する前に昆布を取り出す」とも書いてあります。これはなぜなのでしょうか。
今回は、この疑問に専門的かつ詳しく答えていきます。
昆布の出汁の特徴
昆布にはグルタミン酸という旨味成分が豊富に含まれています。このグルタミン酸は、昆布の独特の風味や旨味を引き出す大切な要素となっております。
しかし、このグルタミン酸は熱に弱い性質を持っており、高温になるとその旨味が失われてしまうのです。
なぜ冷水で昆布を漬けるのか
昆布を冷水に漬けることで、ゆっくりとグルタミン酸を水に溶け出させることができます。この方法により、昆布の旨味を最大限に引き出すことが可能となります。
また、昆布には他にもミネラルやビタミンなどの栄養成分が含まれており、冷水でじっくりと浸けることでこれらの成分もしっかりと取り出すことができるのです。
お湯を沸かしながら出汁をとると…

昆布の出汁を取る際の一般的な方法として、昆布を冷水に浸けてゆっくりと旨味成分を引き出した後、火にかけて温めます。このとき、昆布が沸騰する直前の温度、約80度前後で昆布を取り出すのが一般的です。
これは、昆布自体が煮過ぎると苦味や不要な成分が出るためです。
しゃぶしゃぶや湯豆腐をするときに昆布を入れっぱなしにしておいたほうが良い気がしますが、これは誤りです。お湯が沸騰する前に、昆布は取り出しましょう。
昆布出汁のコツを知っておいしい自炊生活を!
昆布の出汁を取る際には、昆布の旨味や栄養成分を最大限に引き出すため、冷水でゆっくりと昆布を浸ける方法が最適です。お湯を沸かしながらの方法は、昆布の成分が熱によって変質してしまうため、避けるべきです。昆布の出汁を美味しく取るためには、この点をしっかりと理解して、正しい方法で出汁を取ることが大切です。

なるほど、グルタミン酸はお湯に弱いのですね。最後沸騰させて使用しますが、昆布から溶け出したあとは大丈夫なのですか?
はい、その通りです。グルタミン酸は熱に弱い性質を持っていますが、昆布から一度溶け出した後のグルタミン酸は、短時間の沸騰には耐えることができます。
先程述べた通り、水を張った鍋に火を入れたあとは、80度程度まで温まったら昆布を取り出します。
昆布を取り出した後の出汁は、さらに沸騰させることができます。この時点での沸騰は、グルタミン酸の旨味を損なうことはありません。
しかし、長時間の沸騰は避けるようにしましょう。長時間沸騰させると、出汁の風味が飛んでしまう可能性があります。
要するに、昆布から旨味成分がしっかりと溶け出した後の出汁は、短時間の沸騰には問題ありません。ただし、最も美味しい出汁を得るためには、適切な温度管理と時間を心がけることが大切です。

出汁をとった後の昆布を再活用する方法はありますか?
出汁を取った後の昆布は捨てるのはもったいないですね。実は、この昆布は再活用することができ、さまざまな料理に利用することが可能です。以下に、出汁を取った後の昆布の再活用方法をいくつかご紹介いたします。
-
昆布の佃煮
出汁を取った昆布を細切りにし、醤油、砂糖、みりんで煮詰めると、美味しい昆布の佃煮ができます。ご飯のお供や、お酒の肴としても最適です。 -
昆布の炊き込みご飯
昆布を細かく刻み、炊き込みご飯の具材として使用することができます。昆布の旨味がご飯にしっかりと染み込み、深い風味の炊き込みご飯が楽しめます。 -
昆布のサラダ
昆布を細切りにし、きゅうりや人参などの野菜と和えると、さっぱりとしたサラダになります。ポン酢やゴマドレッシングで味付けすると良いでしょう。 -
昆布のスープ
出汁を取った昆布を再び煮込むことで、昆布の風味を活かしたスープを作ることができます。具材として、豆腐や野菜を加えると、栄養満点の一品になります。 -
昆布の天ぷら
昆布を適当な大きさに切り、天ぷら生地で揚げると、サクサクとした食感の昆布の天ぷらができます。塩を振ってシンプルに楽しむのも良いですね。 -
昆布のお茶漬け
出汁を取った昆布を細切りにし、ご飯の上にのせてお茶漬けとしても美味しくいただけます。
出汁を取った後の昆布には、まだ栄養成分や旨味が残っています。再活用することで、これらの成分を無駄なく活用することができるので、ぜひ上記の方法を試してみてください。
また、こちらのレシピも役立つはずです。

#1 出汁がら昆布のポテンシャル。
ソーセージ、マッシュルーム、好みの野菜、出汁がら昆布、オリーブオイル、カレー粉、インスタントラーメン、好みの具、白胡椒、等
出汁をとったあとの出汁がら昆布を活用した3種類のレシピ。出汁がら昆布は野菜と蒸したり、インスタントラーメンに加えたり、お好み焼きと一緒に焼いても合います。…
レシピを見る
#2 出汁がら昆布のサティスファクション。
出汁がら昆布、きくらげ、オリーブオイル、粗挽き黒胡椒、豚ひき肉、片栗粉、砂糖、春雨、赤ピーマン、等
出汁を取った後の昆布で作る、3種類のおつまみのレシピ。使い道がないと思っていた昆布が、お酒のお供に変身します。…
レシピを見る
#3 出汁がら昆布のトランスフォーム。
出汁がら昆布、梅干し、みりん、醤油、八角、大根、米酢またはサラダ油、砂糖、かつお節、等
出汁がら昆布と梅干を活用したレシピ。冷凍した出汁がら昆布と梅干しの佃煮を鍋いっぱいにつくって常備菜に。…
レシピを見る
#4 出汁がら昆布のパースペクティブ。
サバ味噌煮、出汁がら昆布、カレー粉、米油、醤油、黒胡椒、食パン、ウスターソース、粒入りマスタード、等
出汁を取った後の昆布で作る、主食3種のレシピ。出汁を取ってうま味が減った分、サバ缶やトマト、ひき肉でうま味を補います。…
レシピを見る
#5 出汁がら昆布で。昆布の佃煮♪
出汁がら昆布、料理酒、砂糖、醤油、みりん、ごま
昆布を使った、副菜になる佃煮のレシピ。出汁を取った後の昆布を無駄なく活用しているのが特徴。…
レシピを見る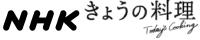
#1 だしがら昆布と実ざんしょうのつくだ煮
昆布、実ざんしょう、しょうゆ、砂糖、みりん
だしをとった後の昆布と実ざんしょうを使った、ごはんのお供にぴったりなつくだ煮のレシピ。だしがら昆布でつくったとは思えない、しっかりした昆布のうま味が味わえます。…
レシピを見る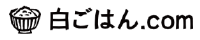
#3 手作りがんもどき
木綿とうふ、にんじん、ごぼう、だしがら昆布、ぎんなん、しょうゆ、山芋、砂糖
おでんや煮物にぴったりのがんもどきを手作りするときのレシピ。揚げたての格別なおいしさを楽しめる一品です。…
レシピを見る

